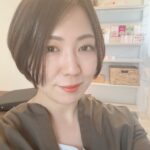
こんにちは!
佐賀市大和町にある鍼灸院PAUME
院長みずたゆいです。
夏休みが明けて、2学期が始まりました。
しかし、休みでリズムが狂ったのか
- 夏休みと変わらず寝るのが遅くなってしまっている
- 朝なかなか起きれない
- 寝ているはずなのに疲れが取れてなさそう。
こういうことでお悩みの方、いらっしゃいませんか?
特に夏休みにありがちなんですが、夏休みだし、遅く寝てるから遅く起きてもいいだろう。と、つい睡眠時間に着目しがちですが、実は、子どもの睡眠は、トータルの時間より、寝始める時間がとても大事なんです。
新学期始まったけど、なかなかリズムを取り戻せないお子さんがいる方にこそ、見ていただきたい内容です。
なぜ《寝始る時間》が大事なのか。
皆さんは、【成長ホルモン】というワードは聞いたことがあるでしょうか。
多分ほとんどの方が聞いたことあると答えるはずです。
ここで一旦、成長ホルモンの作用についておさらいします。
成長ホルモンとは
【成長ホルモンの主な働き】
- 骨や筋肉の成長を促す
→ 子どもが背が伸びたり、体がしっかりしてくるのはこのおかげ。 - 代謝を整える
→ 脂肪を分解してエネルギーに変えたり、タンパク質を作って筋肉や臓器を守る。 - 体の修復をサポート
→ ケガや疲労の回復を助ける。 - 免疫や肌の再生にも関与
→ 大人になっても分泌され続けて、健康や若さを支える。
基本的に成長ホルモンというのは、子どもの成長のために出るホルモン。という認識が一般的かなと思います。
特にこの成長ホルモンは、寝始めの深い眠り(ノンレム睡眠)で多く出るため、夜ふかしして寝始めが遅くなると、このホルモンが出るとされるゴールデンタイムを逃してしまいます。
しかし、先ほど書いた通り、成長ホルモンには成長だけではなく、体の修復をサポートもしてくれるとあります。
つまり、成長だけではなく、体も修復させてくれるからこそ、翌朝スッキリ起きて疲れも取れているということなのです。
なので、寝るのが遅くなることによって、ホルモンの出る量が減少し、成長にも影響しますが、朝起きれない。だるい。集中できない。といったことを引き起こすのだと言えます。
東洋医学の「内臓リズム(子午流注)」から見ても重要
東洋医学では、身体の働きには1日のリズムがあると考えます。
この時間に眠れていると、体の中で血の巡りや解毒がしっかり行われて、成長にもつながります。
時間ごとに体のリズムがあるので、睡眠時間だけを考えればいい。とは言えなくなりますよね。
夏休み後に出やすい、《睡眠の乱れ》サイン
そう言われても、うちの子、遅く寝る割にスッキリ起きれてると思うんだけど…
と思っているそこのママさん。
起きれる以外にも、睡眠が遅いことで出ているサインがあるはずなので、チェックしてみてください。
何個か当てはまる項目はありましたか?
これらのサインは、東洋医学的にも脾胃や肝の働きが乱れているサイン。
私が学んでいる大師流小児はりでも、睡眠不足は内臓機能が低下すると言われ、内臓が本来の働きが出来ておらず、食欲不振や体がしんどくなりやすくなるので、小児はりのような撫でる刺激でもきつく感じたりするお子さんも出てきます。
寝る時間が遅くなることで、影響するものは1つだけではありません。
早く睡眠をとることが難しいお子さんへの東洋医学アドバイス
ここまで書いてきた通り、寝るのが遅くなることが続いてしまうと、寝る時間はしっかり取れても疲れが取れない、スッキリ起きれない、授業に集中出来ないということが起きやすくなります。
そこを解消するためにお家で出来ることを東洋医学を交えながらお話していきます。
夜の照明をやさしくする(陽から陰の切り替え)

東洋医学では昼は陽、夜は陰と言われます。
本来であれば、日が沈むと陰が増して体は休息モードに入ります。
しかし、強い照明やスマホの光=人工の陽を浴びることになり、陰に切り替え出来ず、寝つきが悪いなどの交感神経優位な状態になりやすくなります。
お風呂は寝る1時間前(陽気を収める)

入浴は気血の巡りを一時的に活発にします(陽気を巡らせる)。
そのため、お風呂の直後に寝ようとすると、体がまだ活動モードのためなかなか寝付けないことも…。
入浴後、1時間ほど経つことで、陰が増えて自然と眠りやすくなります。
東洋医学でいうところの、陽気を収め、陰気を養う時間をつくるための工夫ですね。
就寝前のお腹さすり(脾胃をあたため安心感)

実は、東洋医学では子どもは脾虚といって、消化する力がまだ未熟で胃腸が弱りやすい体質が多いと言われています。
お母さんの手で優しくお腹を擦ったり、ただ手を当てるだけで、脾胃を補い、安心感につながる。と言われます。
もちろん小児はりでも、お腹に刺激をしたりあたためたりしますが、お母さんにやってもらったというのがポイント。より安心感に繋がります。
寝つきが悪い・夜中に目が覚める(心・肝・腎のアンバランス)

東洋医学では、眠りは心が落ち着いている状態を指します。
気持ちが高ぶっていたり(心)、ストレスで体の流れが乱れたり(肝)、体のエネルギーが不足していたり(腎)、こうしたアンバランスで眠りが浅くなると言われます。
この高ぶったり乱れた状態を整えたり、自律神経を整えることが出来るのが小児はりです。陰陽・気血のバランスをしっかり取り戻します。
まとめ|《睡眠の長さ》より《寝始める時間》を意識
ではまとめに入ります。
- 成長ホルモンは寝始めの深い眠りでしっかり出る
- 東洋医学の内臓リズム(胆・肝)から見ても、夜の早い時間に眠ることが大切
- 夏休みで崩れたリズムは、照明・入浴タイミング・お腹さすりなどの小さな工夫で戻りやすい
それでも整いにくいときは、小児はりで「眠れる体」づくりをサポートします!
「分かってはいるけれど、家ではうまく進まない…」
そんなときでも大丈夫!
出来ない…!と、自分を責めないで、小児はりに早めに頼るのも鍵です。
まずはご相談からでも、気軽にご連絡くださいね。
ご予約はこちらのLINEから
ご予約や何か気になること、ご質問など、こちらのLINE登録後、ご気軽にご連絡ください。
登録後、一言メッセージをいれていただけると、こちらから返信可能となりますのでよろしくお願いいたします。




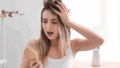
コメント